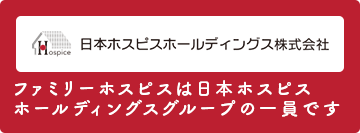ファミリー・ホスピスとは

ファミリー・ホスピスは「おうち」と「病院」のいいとこどり
自由に生きる
ぜんぶ自分で決める、そして自分で責任をとる
ファミリー・ホスピスチームがいつも近くにいてくれる
看護師、療法士、介護士、調理師、事務員の専門職チームだから安心
コミュニティの中で暮らすっていいなあ
家族がそばにいてくれる
親戚も、友達も、近所の人も来てくれる
みんなが笑顔
ファミリー・ホスピスチームは地域との架け橋
近くのお医者さんやケアマネさんも来てくれる
みんなが親切、みんなが笑顔
ときどき、お出かけ
どうしても行きたかった、お墓参り
“いずれ私もお世話になります”
自分でできることは自分でやってみる
家族ができることは家族がやってくれる
そしてファミリー・ホスピスチームはやさしく包んでくれる
ファミリー・ホスピスは「おうち」と「病院」のいいとこどり
「おうちが病院」っていいなあ
自由に生きる
ぜんぶ自分で決める、そして自分で責任をとる
ファミリー・ホスピスチームがいつも近くにいてくれる
看護師、療法士、介護士、調理師、事務員の専門職チームだから安心
コミュニティの中で暮らすっていいなあ
家族がそばにいてくれる
親戚も、友達も、近所の人も来てくれる
みんなが笑顔
ファミリー・ホスピスチームは地域との架け橋
近くのお医者さんやケアマネさんも来てくれる
みんなが親切、みんなが笑顔
ときどき、お出かけ
どうしても行きたかった、お墓参り
“いずれ私もお世話になります”
自分でできることは自分でやってみる
家族ができることは家族がやってくれる
そしてファミリー・ホスピスチームはやさしく包んでくれる
ファミリー・ホスピスは「おうち」と「病院」のいいとこどり
「おうちが病院」っていいなあ
ホスピス住宅が求められる背景と、私たちのビジョン
日本は超高齢社会への対応に追われていますが、今後より問題となるのが「多死の時代」への対応です。終末期を見据えた生き方、死に方、死に場所をどう考え、どう向き合うかが問われています。
がん患者を対象とした緩和ケア病棟(ホスピス病棟)の整備は進みましたが、多くの国民が望む”終末期を自宅で療養したい、最期を自宅で迎えたい”に応える「ホスピス住宅」サービスは非常に脆弱です。住み慣れた家や、高齢者住宅に自宅を移してのホスピス住宅を当社は日本に根付かせたいという思いで研究と普及活動をしていきます。
がん患者を対象とした緩和ケア病棟(ホスピス病棟)の整備は進みましたが、多くの国民が望む”終末期を自宅で療養したい、最期を自宅で迎えたい”に応える「ホスピス住宅」サービスは非常に脆弱です。住み慣れた家や、高齢者住宅に自宅を移してのホスピス住宅を当社は日本に根付かせたいという思いで研究と普及活動をしていきます。

日本は、超高齢社会に突入しています。65歳以上の高齢者は全人口の25%を超え、それにともない2050年頃までに死亡者数は増え続けるともいわれています。

厚生労働省は、病院ではなく、在宅での療養・看取りを推進しています。「家で最期を迎えたい」というニーズもますます高まっており、在宅で安心して療養できる仕組みが求められています。

近年、高齢者の暮らしを支える「地域包括ケアシステム」が推進されており、医療・介護従事者をはじめ、行政職員、地域住民などが連携し、高齢者が住み慣れた地域で最期まで自分らしく暮らせる仕組みが整いつつあります。

私たちは、がんや難病といった緩和ケアを必要とする患者が、最期まで自分らしく暮らせるようなホスピス住宅サービスを提供しています。いずれは、地域における「在宅での最期のとき」をプロデュースする存在になることを目指しています。
ホスピス住宅を支える多職種
看護師
終末期においては、病状の急変など予測できないことが起こる場合も多いため、看護師の適切な判断と行動が非常に重要です。施設内の他職種はもちろん、在宅医や医療機関とも連携して、最後まで「おうち」で安心して暮らせるようなケアを提供しています。
当グループでは、緩和ケアや訪問看護の経験がある看護師だけでなく、急性期病院で経験を積んできた看護師や、認定看護師・専門看護師など、様々なバックグラウンドを持った看護師が活躍しています。
当グループでは、緩和ケアや訪問看護の経験がある看護師だけでなく、急性期病院で経験を積んできた看護師や、認定看護師・専門看護師など、様々なバックグラウンドを持った看護師が活躍しています。
介護士
ケアマネジャーのケアプランに沿って、食事や排泄、入浴など、日常生活の様々な行為をサポートする介護士は、ホスピス住宅を支える職種のなかでも利用者の方との距離が近い存在といえます。訪問する回数も多いため、利用者の方の率直な思いを聴く機会も多いです。当グループのスタッフは、仕事としてケアを行うだけでなく、本人やご家族との会話を楽しみ、その会話のなかから、その方らしく過ごしていただくためにはどうしたらいいかを自然に考えて働いています。こうした姿勢が、最後までその方らしい暮らしを実現することを支えています。
療法士
理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が、ケアマネジャーのケアプランに沿って、支援を行っています。例えば、食事や排泄など日常生活を行う上で必要な動作のリハビリや、嚥下リハビリ、拘縮予防、疼痛軽減のためのマッサージなどを行っています。
また、難病の方に対するリハビリも行っています。神経難病の多くは進行性で、身体機能が徐々に低下していきますが、そのなかでも療養生活を快適に過ごしていただくために、呼吸に関するケアを行ったり、適切な栄養摂取方法を提案したり、コミュニケーション方法を提案・訓練したりするなど、専門性を活かした働きかけをしています。
また、難病の方に対するリハビリも行っています。神経難病の多くは進行性で、身体機能が徐々に低下していきますが、そのなかでも療養生活を快適に過ごしていただくために、呼吸に関するケアを行ったり、適切な栄養摂取方法を提案したり、コミュニケーション方法を提案・訓練したりするなど、専門性を活かした働きかけをしています。
その方らしい生活を支援する
私たちはこれまで、利用者さんやご家族の様々な希望を実現してきました。
ここではそのエピソードをご紹介します。
ここではそのエピソードをご紹介します。
エピソード1:家族の負担を軽減しつつ、本人のやりたいことを後押しする

清さん(仮名)のケース
70代男性。ALSの診断を受け、自宅で療養していたが、病気が進行するにつれて介護する妻の負担が大きくなり、訪問看護師の紹介で入居。
70代男性。ALSの診断を受け、自宅で療養していたが、病気が進行するにつれて介護する妻の負担が大きくなり、訪問看護師の紹介で入居。
ALSの診断を受け、自宅で療養していた清さん。妻は、何とか自宅で看たいという思いと、家族だからという責任感を持ちながら介護を続けていたが、疲弊が限界を迎え、清さんの入居を決断した。
清さん自身が入居を希望したわけではなかったため、入居後しばらくは不安の方が強く、昼夜問わず頻繁にナースコールがあった。なかなかスタッフに心を開かなかったが、入居して3か月ほど経つと、徐々にスタッフとの信頼関係ができていった。
家族は、少しでも清さんが快適に過ごせるようにと、外出やコミュニケーション支援ツールの使用を清さんに幾度となく促しているが、本人はなかなか前向きになれない状態が続いている。ただ、航空自衛隊のショーだけは特別だ。航空機の動画を見るために視線入力のツールを使ってみるなど、物事に挑戦するモチベーションになっている。また、スタッフと話が盛り上がったことをきっかけに、清さんは航空自衛隊のショーの障害者招待枠の抽選に応募した。
この時ばかりは、普段ベッドで横になっている清さんもご家族も奮起して、車椅子で過ごす時間を積極的に作った。残念ながら抽選には外れてしまったが、これを機に外に出られるようにと外出の練習を続けている。
清さん自身が入居を希望したわけではなかったため、入居後しばらくは不安の方が強く、昼夜問わず頻繁にナースコールがあった。なかなかスタッフに心を開かなかったが、入居して3か月ほど経つと、徐々にスタッフとの信頼関係ができていった。
家族は、少しでも清さんが快適に過ごせるようにと、外出やコミュニケーション支援ツールの使用を清さんに幾度となく促しているが、本人はなかなか前向きになれない状態が続いている。ただ、航空自衛隊のショーだけは特別だ。航空機の動画を見るために視線入力のツールを使ってみるなど、物事に挑戦するモチベーションになっている。また、スタッフと話が盛り上がったことをきっかけに、清さんは航空自衛隊のショーの障害者招待枠の抽選に応募した。
この時ばかりは、普段ベッドで横になっている清さんもご家族も奮起して、車椅子で過ごす時間を積極的に作った。残念ながら抽選には外れてしまったが、これを機に外に出られるようにと外出の練習を続けている。
エピソード2:最期まで食事を楽しめるよう支援する

静枝さん(仮名)のケース
80代女性。多発性骨髄腫で余命1か月と宣告されたが、入院生活でのQOLの低下を心配した娘・桂子さん(仮名)の希望で入居
80代女性。多発性骨髄腫で余命1か月と宣告されたが、入院生活でのQOLの低下を心配した娘・桂子さん(仮名)の希望で入居
多発性骨髄腫で入院した静枝さん。せん妄が出て、身体拘束を受ける姿に娘の桂子さんは耐えきれず、ハウスへの入居を決断した。
ハウスの近くには川があり、スタッフが入居したての静枝さんに「気分転換に行ってみる?」と声をかけたのが、元気を取り戻すきっかけになった。スタッフ間での調整を行い、酸素機器や尿道カテーテル等の本人が嫌がる医療措置を、リスクを考慮しつつできるだけ外していく。手すりの設置とリハビリにより、トイレにも一人で行けるようになった。
入院時は食欲がなかった静枝さんだが、食卓で周りの人が食べるのを見ると不思議と皿に手が伸びる。入居半年後には「(好きだった)お寿司が食べたい」と言い出すほど食欲が回復した。スタッフは車椅子でも入れる寿司屋を探し、静枝さんを連れて出かけた。静枝さんはスタッフが心配するほどの量をぺろりと平らげる。帰りに散歩に寄った公園では、車椅子を降りて歩き出すほど気分が良くなった。
気力と体力の回復が押しとどめていたとはいえ、病は少しずつ進行していた。骨折のリスクはあったが、部屋で食べるのは寂しいと、昼だけでも部屋から出て食べていた。幸い誤嚥もなく、様々な症状を緩和しつつ、静枝さんは最期まで食事を楽しむことができた。
ハウスの近くには川があり、スタッフが入居したての静枝さんに「気分転換に行ってみる?」と声をかけたのが、元気を取り戻すきっかけになった。スタッフ間での調整を行い、酸素機器や尿道カテーテル等の本人が嫌がる医療措置を、リスクを考慮しつつできるだけ外していく。手すりの設置とリハビリにより、トイレにも一人で行けるようになった。
入院時は食欲がなかった静枝さんだが、食卓で周りの人が食べるのを見ると不思議と皿に手が伸びる。入居半年後には「(好きだった)お寿司が食べたい」と言い出すほど食欲が回復した。スタッフは車椅子でも入れる寿司屋を探し、静枝さんを連れて出かけた。静枝さんはスタッフが心配するほどの量をぺろりと平らげる。帰りに散歩に寄った公園では、車椅子を降りて歩き出すほど気分が良くなった。
気力と体力の回復が押しとどめていたとはいえ、病は少しずつ進行していた。骨折のリスクはあったが、部屋で食べるのは寂しいと、昼だけでも部屋から出て食べていた。幸い誤嚥もなく、様々な症状を緩和しつつ、静枝さんは最期まで食事を楽しむことができた。